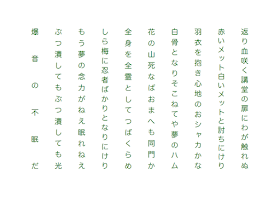寺山修司にとっての川柳
福田若之
俳句というジャンルの芸術的価値の問題を取り扱う上で、桑原武夫の「第二芸術」ばかりを取り上げて寺山修司「川柳の悲劇――現代俳句の周囲」(初出は「青高新聞」1954年2月9日。本稿での引用は『寺山修司の俳句入門』、光文社、2006年に基づく)を取り上げることがないのだとしたら、この問題の一面ばかりを強調することになってしまうだろう。寺山の俳句に心揺さぶられる身としては、同じ寺山の書きものをこのように取り上げるのはどうも心苦しいのだけれど、それでも取り上げないわけにはいかない。寺山はこの文章で、桑原が芸術の名の下に俳句を非難したのとほとんど同様の仕方で、俳句の名の下に川柳を非難しているように見える。
両者に共通しているのは、取りあげる二つの領域(桑原の場合は西洋近代芸術と現代俳句、寺山の場合は現代俳句と現代川柳)が別物であるという認識を補強しながら、直ちに一方を他方よりも程度の低いものとして立ち上がらせ、その結果、ついにはその対象を芸術や文学からほとんど締め出してしまうことである。
寺山は、文章の冒頭で俳句と川柳が接近していることについて述べる佐藤狂六の文章を引用し、その上で、「私はそれを読んだあとで、この程度の川柳が現代俳句への接近といわれ、それによって現代俳句の限界が価値づけられることのおそろしさと、川柳作家たちの自己満足への不服から一寸したラクガキをしてみる気になった」(49頁)と書いている。ここで、「現代俳句の限界」という表現に、はっきりと「第二芸術」の文脈を見て取ることができる。そして、この寺山の文章を「第二芸術」の文脈から捉え直すとき、寺山の狙いは現代俳句を現代川柳から切り離すことで芸術への回帰を図らせることだったのではないかと思われて来さえする。だが、もし、第二芸術として告発された現代俳句がその称号を現代川柳に押し付けることによってその芸術性を主張するのだとしたら、それは恥ずべきことではないだろうか。
寺山はこう書く。
私が川柳の文学性の欠点を指摘するのはつぎの点からである。第一に川柳は五・七・五のわずか十七文字に限られていること、そしてその十七文字が江戸の柄井川柳の始めから二十世紀の今まで、一つの切れ字も公認されていないことである。(49頁)要するに、俳句との違いは「切れ字」という体系の有無だということになる。しかし、直感的にも明らかなように、それは俳句と川柳の傾向的な違いでこそあれ、川柳が俳句よりも劣っていると主張することの客観的な根拠にはならない。「切れ字」がないことには芸術上の欠点ばかりではなく、利点を見出すこともできる。たとえば、それは修辞に関してのより柔軟な選択を可能にするだろう。
寺山は「川柳の切れ字なしの法則は、江戸以来のマンネリズムをかもしだした最も大きな原因となるだろう」(50頁)という。しかし、俳句の切れ字もまたそれによって江戸以来のマンネリズムをかもしだしていないなどと主張することが果たしてできるのだろうか。確かに、現代俳句は、いかに切れ字をマンネリズムから逸脱させるか、絶えず試行錯誤してきた〔*〕。しかし、それはまた、切れ字による様式化が俳句を容易にマンネリズムへと導きうることを意味してもいるのではなかっただろうか。
寺山は「つまり川柳が同じ五・七・五を保ちながら、発生以来、芸術らしき所作を避けたために、それ自体作家の哲学性をも、美術、音楽性をも、発酵させるには至らなかったことを私はかなしみたいのである」(50頁)という。これはほとんど、芭蕉の死後の発句と俳句についての桑原の批判を要約し、その主語を川柳に置き換えたものに等しい。
確かに、寺山にとっての川柳のほうが桑原にとっての俳句よりも芸術的価値を持つ余地がある。寺山は、そのために「第一に知性をもちたいということ、更に一つの方向と課題をもつことである」(51頁)という。しかし、寺山の文脈では、この言葉は川柳の敗北を決定的にする。なぜなら、ここで手本として示されるのは他ならぬ俳句だからだ。「俳句には一定の課題がないが俳人には大抵、一定の課題がある」(51頁)。
実際、俳句と川柳の差異を寺山のように捉えてしまうなら、「よし川柳が俳句的な風景描写をこころみたとしても、その裏に思想や自己抽出がなければ無価値であり、もしあったならば、それは川柳ではなくて、俳句になっているだろう」(50-51頁)ということにもなる。だが、寺山の議論はまさしくこの一文においてその欺瞞を露呈している。寺山は、五・七・五の形式をもつジャンルを彼にとって価値のあるものと価値のないものとにあらかじめ二分し、片方を「俳句」、もう片方を「川柳」と呼びながら、後者を価値がないとして非難しているのである。
だから、価値ある「俳句」と無価値な「川柳」という対立は、「川柳の悲劇」の中では決して覆ることがないようにあらかじめ仕組まれている。これはボクシングではなくプロレスであって、「川柳」が打倒されるのはそういう役回りであるからに過ぎない。おそらく、十八歳の寺山には、俳句が芸術であるためには俳句が何かに勝つ必要があると思われたのだ。言ってみれば、「川柳の悲劇」とは彼がそのために企画した興行であって、そのために他所から呼ばれたヒールが「川柳」だったのである。
覆面レスラーはマスクを被ってはじめて一人のレスラーとしてリングに立つことができる。ザ・デストロイヤーはトレードマークの白い覆面がなければただの人間になってしまうのであり、その意味で、彼のアイデンティティはその覆面にあるといっていい。「川柳の悲劇」の舞台における「川柳」という名は、こうしたレスラーの覆面に等しいものだ。寺山は、批判対象であるはずの川柳の具体例に一切触れない。それはおそらく、この文章で「川柳」と呼ばれているものが、実際には、ただ曖昧な観念として準備されたものにすぎないからだ。「川柳」という名、この覆面によってはじめて、ひとつの観念が確かなキャラクターを獲得し、リングに上がることを許される――あらかじめ運命づけられた敗者として。寺山は文章の終わり近くで、川柳とは「詩のない文学、切れ字と季感のない俳句」(51頁)だと書く。しかし、得られた結論に見せかけられたこのことこそ、実は、彼にとっての前提条件にほかならないのだった。
●
とはいえ、これで終わりではない。
寺山は、1956年12月の「カルネ――〈俳句絶縁宣言〉」を経て、やがて川柳にも一つの積極的な価値を見出すようになる。「ANDER-DOGたち」(綴りは原文ママ。初出は「俳句研究」1959年12月号、本稿での引用は前掲の『寺山修司の俳句入門』に基づく)と題された日記体の断章集から、ひとつの挿話を取り上げてみよう。
×月×日
「天馬って知ってるか」
と友人が言った。
「川柳の雑誌だ」
「あゝ」と僕は答える。
「意欲的なやつだな」
「(天馬の行き方は声明にあった如く、川柳とは一線を引いた行き方になっています。これは詩性を重要視するからです)ってかいてあったぜ」
「川柳は落書きだ」と僕は呟く。
「え?」
「川柳までお芸術になることはないんだ」
彼は壁にかけてある僕のバンジョーをはずしてばらばらんとならした。
「そんなもんかな」
「そうとも」と僕はつけ加えて、「川柳の生き残る道は、万人が作者になり、歴史というとてつもない大きな土蔵の壁に落書することなんだ」
「観念的な奴だな」と彼は笑った。
「この頃の川柳は前衛俳句と変らんぜ」
「だからこそ」と僕は言う。
「俳句は呪文のように難解になればいいさ。キサスキサスだのケセラセラだのという言葉のように生という宗教の呪術になってしまって芸術性を獲得してもいい。だが川柳は、川柳はちがう」
「いやに川柳を買い被ったね」
「川柳は批評だ」と僕は言った。
「いいか、もし川柳に独自性を見出すとしたらそれは対象を批評で変革しようという意志をシンプルにしたものだ。落書の精神だ」
「芸術じゃいかんのか」
「きみは芸術を買い被りすぎているんだ」
彼はまたバンジョーを鳴らした。
ばらん、ばらん。
(154-156頁。原文では強調部は傍点)
ここで彼が川柳をあくまでも芸術ではないというのは、かつての主張の繰り返しではなくて、川柳に積極的な価値を見出すための口実になっている。すべての人が作者として歴史に落書するという企図は、僕には芸術の――ではないのだとしても、少なくとも芸術的な――それに思える。「芸術」を名乗ることに伴う気取りを批判する姿勢は、いわばダダイスティックなポーズであって、そこにはやはり別の芸術があるのではないだろうか。僕は芸術を買い被りすぎているんだろうか。寺山は、川柳とは落書きであり批評であるという。彼が「川柳の悲劇」で自らの批評を「ラクガキ」と呼んでいたことを思うとき、この言葉の選択は軽視できない。 寺山は、現在の彼にとっての「川柳」を、「川柳」について語った5年前の自らの文章とひとつにする。彼にとっての「川柳」は依然として観念的でありつづけるが、この同一化によって、彼はひとつの立場を選び取ることになる。それは、敗者の美学を肯定し、自らのものとする立場だ。それこそは、愛すべき敗者としての悪役レスラーの立場にほかならない。
もしかすると、それゆえにこそ「負け犬」を意味する"UNDER-DOG"は"ANDER-DOG"と綴られたのかもしれない。スペルミスとは、言語における正統なものからの逸脱にほかならない。寺山にとって、俳句との絶縁は、多かれ少なかれ、そうした正統からの逸脱だったのではないだろうか。寺山の選択が川柳にとって幸福なことだったのかどうか、また、俳句にとって幸福なことだったのかどうか、あるいは、批評にとって幸福なことだったのかどうか、そしてなにより、寺山にとって幸福なことだったのかどうか。それは僕には分からないけれど。
〔*〕寺山は切れ字が効果的に用いられている俳句の例として加藤楸邨の〈死ねば野分生きてゐしかば争へり〉と、山口誓子の〈海に鴨発砲直前かも知れず〉を、それぞれの上の句の直後の切れを「、」で示しながら引用している(ただし、楸邨の句は〈死なば野分、生きていしかば争へり〉と、不正確に引用されている)。寺山がここで引用している二句の書き手がいずれも「第二芸術」での不名誉な例示を免れている作家であることは注目に値する。
もしかすると、それゆえにこそ「負け犬」を意味する"UNDER-DOG"は"ANDER-DOG"と綴られたのかもしれない。スペルミスとは、言語における正統なものからの逸脱にほかならない。寺山にとって、俳句との絶縁は、多かれ少なかれ、そうした正統からの逸脱だったのではないだろうか。寺山の選択が川柳にとって幸福なことだったのかどうか、また、俳句にとって幸福なことだったのかどうか、あるいは、批評にとって幸福なことだったのかどうか、そしてなにより、寺山にとって幸福なことだったのかどうか。それは僕には分からないけれど。
〔*〕寺山は切れ字が効果的に用いられている俳句の例として加藤楸邨の〈死ねば野分生きてゐしかば争へり〉と、山口誓子の〈海に鴨発砲直前かも知れず〉を、それぞれの上の句の直後の切れを「、」で示しながら引用している(ただし、楸邨の句は〈死なば野分、生きていしかば争へり〉と、不正確に引用されている)。寺山がここで引用している二句の書き手がいずれも「第二芸術」での不名誉な例示を免れている作家であることは注目に値する。