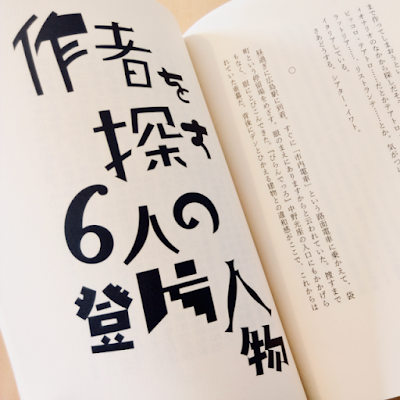火蛾は火に裸婦は素描に影となる 岡田一実(以下同)
巻頭の句である。「火蛾は火に」で切れるという読みもあり得るが、「火蛾は火に」と「裸婦は素描に」とが助詞を揃えた対句で、両方が下五の「影となる」にかかると見るのが順当だろう。しかしながら「火蛾は火に/影となる」と「裸婦は素描に/影となる」は「影となる」のありようが全然違う。前者は単に火という光源に対し火蛾が光源を遮ることを言っているのに対し、後者は光源を遮るという意味ではあり得ない。芸術作品の完成度に関わる内面的な描写のことを言っている。次元の異なるものをあえて対句とすることにより、この句自体が曰く言い難い影をまとっている。そして句集を読み進めるにつれ、その曰く言い難い影と、もうひとつ、ある種の水分がまさに句集のタイトル通り「記憶における沼」のように繰り返し現れるのに読者は直面することになる。巻頭の句にふさわしい一句であろう。
眠い沼を汽車とほりたる扇風機
二句目で「記憶における沼」の核たる「沼」が出現する。「眠い沼」とは現実界の沼に対する措辞なのか、それとも心象なのか。そのあたりはっきりしない茫洋とした感じこそがこの句の味なのだろう。ノスタルジックに汽車が通り、人がいるのかいないのかも定かでない世界で扇風機が回っている。
蟻の上をのぼりて蟻や百合の中
全句鑑賞になってしまいそうな勢いで恐縮だが、三句目も押さえておこう。この句では句集全体を通じて見られる外形的な特徴がはっきり見てとれる。ひとつはリフレインである。以前『ロボットが俳句を詠む』の連載で後藤比奈夫について書いたことがあったが、そこで触れたリフレイン技法のすべてを岡田一実はマスターしている。巻頭の「火蛾は火に」など、むしろリフレインの新たな領域を開拓している感もある。もうひとつの特徴を言えば、十七音の調べの中で岡田一実のいくつかは、短い単位をこれでもかと詰め込んだ感がある。とりわけ下五への詰め込み効果については別の句を例にあらためて触れたい。
●
以下、章ごとに見て行きたい。第1章は「暗渠」。暗渠とはいうまでもなく、川を治水、衛生、交通などの観点から上にふたをして見えなくしたもの。川としてなくなった訳ではなく、暗いところで脈々と流れているところが眼目である。普段気にかけることはないが確実に存在するものへのまなざしは、岡田一実にとってもテーマであろう。
暗渠より開渠へ落葉浮き届く
治水行政が進んでしまったので、暗渠から開渠に転じる場面はそうあるわけではないが、あるところにはある。流れ出た落葉を見て、暗渠区間の様子に思いを馳せている。「浮き」「届く」と動詞を畳みかけることにより、着地を決めている。とりわけ「届く」が絶妙である。
喉に沿ひ食道に沿ひ水澄めり
水を飲んだときの快感を詠んでいるが、詠みようは暗渠の句と同じで、体内の見えない器官に思いを馳せている。「水澄む」は伝統的には地理の季語であるが、もはやなんでもありである。ちなみに章に六十句ほどあるうち、二十句近くはリフレインや対句を使用している。いかにその技法にかけているかが偲ばれる。
馬の鼻闇動くごと動く冷ゆ
馬にぎりぎりまで迫って詠んでいる。馬に慣れ親しんだ人ならこうは詠まないだろう「闇動くごと動く」の違和感、下五に押し込めた「冷ゆ」が喚起する鼻息の温度差、湿度差がよい。下五の残り二音で切れを入れて来る、この危ういバランス感覚はリフレインへの信頼があるからできることなのかも知れない。「闇動くごと動く」に律動的に現れるgo音がなんとも不気味である。
●
第2章は「三千世界」。現代国語例解辞典(小学館)から引く。①「三千大千世界」の略。仏教の想像上の世界。須弥山を中心とする一小世界の千倍を小千世界、その千倍を中千世界といい、更にそれを千倍した大きな世界をいう。大千世界。②世界。世間。「三千世界に頼る者なし」
①の説明によれば、三千というより、千の三乗、ギガワールドである。章中「三千世界にレタスサラダの盛り上がる」という句がある。外食業界で一時期、大盛りの極端なのを「メガ盛り」とか「ギガ盛り」とか言っていたような気もするが、それはさておき「三千世界」、どんなバラエティの世界なのか見て行こう。
夢に見る雨も卯の花腐しかな
甘美である。夢と現実とが「卯の花腐し」という古い季語によって融けあっている。「夢に見る雨も」に現れるm音の連鎖と「夢」「卯の花」「腐し」で頭韻的に現れる母音u音によって、やわらかな雨のなかにとろけてゆくようである。
早苗饗や匙に逆さの山河見ゆ
こちらは徹底的に頭韻にsa音を置いて調べを作っている。早苗饗は田植えが終わった祝い。ほんとうに匙に逆さの山河が見えたのかはどうでもいいことだろう。音韻的な美意識によって句集に彩りを添えている。
あぢさゐの頭があぢさゐの濃きを忌む
リフレインの句である。「あぢさゐの頭」は植物としてのアジサイの意思なのか、七変化する作者の意識のことをそう呼んでいるのか。もはや区別する必要もないのが、作者にとっての「三千世界」なのではないか。
夕立の水面を打ちて湖となる
湖に降る夕立は、ただちにそのまま湖水となる。明らかなことがらをあえて俳句に仕立てているわけだが、このように書かれると、夕立と湖が一体となる不思議を思う。ここでも「夕立」「打ちて」「湖」と母音u音を畳みかけて調べを作っている。
母と海もしくは梅を夜毎見る
三好達治「郷愁」の一節に「――海よ、僕らの使ふ文字では、お前の中に母がゐる。/そして母よ、仏蘭西人(フランス)の言葉では、あなたの中に海がある。」があるせいで、後から来た私たちは類想を封じられてしまった感もあるのだが、岡田一実はさらにこれでもかと「梅」「毎」を重ね、あっさりとハードルを越えてしまった。
どうだろう。なにかしら言い止めるべき現実があって俳句をものしていると思っていると、岡田一実の表現しようとしていることは捉えられないのではないか。岡田一実の「三千世界」は俳句としての調べや表記の純度を追求した、架空の世界のような気がする。
●
第3章は「空洞」。何句かごとに鳥が飛び、ひとところに留まらない。
麺麭が吸ふハムの湿りや休暇果つ
岡田一実の食べ物の句は必ずしも美味しそうでない。つきまとうノイズのようなものを正確に捉えている。朝作ってもらったお弁当のパンを昼食べるときの情けないようなだらしないような感じ。その通りなんだけど、それ、詠みますか。
口中のちりめんじやこに目が沢山
すでに口のなかに入っているのにちりめんじやこの目の気持ち悪さに言及してやまない、この感じ。「栄養なんだから食べなさい」と叱られる子どもの恨みのようである。
かたつむり焼けば水焼く音すなり
これは食べ物の句なのか。エスカルゴとは書いていない。あえてかたつむりと書きたかったのではないかという気もする。食べ物の句だとしたら、いかにも不味そうである。ちなみに俳句にとってはどうでもいいことだが、ネットによれば、自分で採ってきたカタツムリを食べるには、二三日絶食させるか清浄な餌を食べさせ続ける必要があるらしい。
火を点けて小雨や夜店築くとき
「水焼く」といえば、こんな句もある。また最終章には「雨脚を球に灯せる門火かな」というあまりにもうつくしい句がある。なにかしら煩悩のように、気がつくとまたしても水がある感じ。それが記憶の沼につながって行くのかも知れない。
煩悩や地平を月の暮れまどひ
「くれまどう」は通常「暗惑う」「眩惑う」と書き、悲しみなどのために心がまどう、どうしたらよいか、わからなくなる、といった意味だが、ここでは敢えて「暮れまどひ」と書き、月が暮れることができないというシュールな情景を重ねている。
室外機月見の酒を置きにけり
かと思うとこんな句も。こんなふうに風流に詠まれた室外機を私は知らない。
ちりぢりにありしが不意に鴨の陣
ここまで挙げたような日常些事から心象まで多岐にわたる対象世界を、いちいちご破算にするかのように数句ごとにさまざまな鳥が飛ぶ。掲句以外にも「常闇を巨きな鳥の渡りけり」「飛ぶ鴨に首あり空を平らかに」「歩きつつ声あざやかに初鴉」など。句集におけるこういう鳥の使われ方は、見たことがなかったような気がする。
揚花火しばらく空の匂ひかな
この章の最後を飾る句である。「火薬の匂ひ」ではない。「空に匂ひ」でもない。書かれた通り「しばらく」、「空の匂ひ」と置かれた六音を書かれた通り玩味する。そして記憶の中をさまよう。幼年期の記憶は理路整然と分析できない渾然一体の「空の匂ひ」としか言いようのないものだ。そして詠嘆する。
●
最終章は「水の音」。特に章頭の句「海を浮く破墨の島や梅実る」と句集全体の最後を飾る「白藤や此の世を続く水の音」に見られる「を」について注目したい。これらの「を」は岡田一実にとって万感の「を」であり畢生の「を」であるはずだが、現代日本語としてはいささか尋常ではないようだ。
『岩波古語辞典』の巻末の基本助詞解説によれば、格助詞の「を」は本来、感動詞だったものがやがて間投助詞として強調の意を表すようになったらしい。そこからさらに目的格となるくだりを少し長くなるが引用する。
こうした用法(ゆかり註。間投助詞として「楽しくをあらな」のように使われていたことを指す)から、動作の対象の下において、それを意識するためにこの語が投入された。そこからいわゆる目的格の用法が生じたものと思われる。しかし、本来の日本語は目的格には助詞を要しなかったので、「を」が目的格の助詞として定着するにあたっては、漢文訓読における目的格表示に「を」が必ず用いられたという事情が与っていると思われる。
対象を確認する用法から、「を」は場合によっては助詞「に」と同じような箇所に使われる。たとえば、「別る」「離る」「問ふ」などの助詞の上について、その動作の対象を示すのにも用いる。また、移動や持続を表す動詞の、動作全体にわたる経由の場所・時間を示すことがある。
後者の例として以下が挙げられている。「天ざかる鄙の長道を恋ひ来れば明石の門より家のあたり見ゆ」<万三六〇八>「長き夜を独りや寝むと君が言へばすぎにしひとの思ほゆらくに」<万四六三>
違和感ゆえに詩語として絶妙に意識させられる岡田一実の「を」は万葉集由来のものだということらしい。「移動や持続を表す動詞の、動作全体にわたる経由の場所・時間を示す」という用法を頭に叩き込んでおこう。
海を浮く破墨の島や梅実る
破墨は水墨画の技法だから、一幅の作品に対峙していると見るのが順当だろう。描かれたときから作品の中でそうあり続けている海と島の玄妙な関係に思いを馳せる。そんな時の流れを想起させもする「梅実る」がよい。モノクロームの世界に取り合わせられるふくよかな緑。
白藤や此の世を続く水の音
過去から未来までの長大なスケールの中での自分が今生きているこの一瞬。水がある限り白藤を愛でることができる生命体が長らえる。句集の最後を飾る、そんな万感の「を」だと思う。